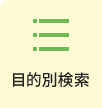地場産業
更新日:2025年9月1日
藍染め
埼玉県の染色業は、武州正藍染、熊谷染、草加本染浴衣などがあります。八潮市は草加市、越谷市、吉川市、三郷市、川口市などの草加本染浴衣の染色地域に属します。
八潮市の浴衣の染色業は、長板中型と注染があり、注染は大正10年ごろから起こり浴衣染めの主流となりました。注染が起こると長板中型は減少の一途をたどりました。
では、なぜ染色業が盛んになったのでしょう。
- 木綿を栽培し機織の多い栃木、群馬、埼玉の畑作地と消費地東京の中間に位置している。
- 農閑期の余剰労働力がある。
- 形付けの糊の原料の糯米や武州藍の生産地である。
- 木綿の和晒の盛んな増林や瀬崎に近接している。
- 中川、綾瀬川、葛西用水の軟水の水が豊富である。
などの諸条件が整っていたからです。
市内の長板中型染の伝承技術者として、初山寛さんと大熊敏男さんが埼玉県の無形文化財に指定されています。